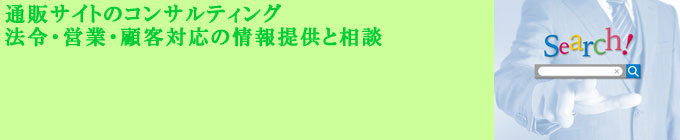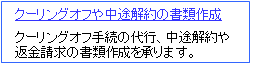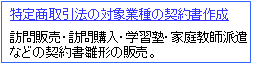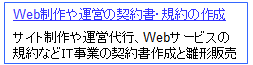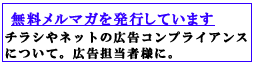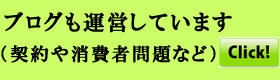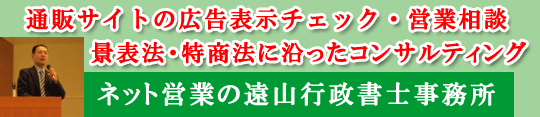
訪問販売によるトラブルの相談件数は、国民生活センターの消費生活年報2009年度版によれば97,382件になっています。
これはピーク時の2003年度の184,817件と比較すると47%減少していますが、まだ多くの相談が消費生活センターに持ち込まれています。
訪問販売トラブルの相談が減少した要因としては、幾度の特定商取引法等の改正により事業者の規制と消費者保護の民事ルールが強化されたことが挙げられます。
クーリングオフ制度や過量販売解除権などの制定により、強引な勧誘によって売買契約をしても、消費者側からの契約解除が認められるので、事業者がそのような悪質な販売方法を行うメリットが無くなりました。
しかし、それでも訪問販売の契約トラブルは多く発生しています。
前掲の年報によれば、訪問販売の相談件数のうち60代以降の占める割合が48%にも上っています。
特に退職金や年金などの資産を持ち、判断力が劣った高齢者世帯が悪質な訪問販売事業者のターゲットになっていることが浮き彫りになっています。
また、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)では、2014年度においては訪問販売は約89,000件、電話勧誘販売では約90,600件の苦情相談が寄せられていることが確認されています。
このうち訪問販売協会会員企業に関する苦情は1.45%に過ぎず、大部分が非会員の事業者によるトラブルであることも確認されています。
つまり、訪問販売業でも適正な運用に努める事業者が問題を起こすことは少なく、法令遵守の意識が低い事業者が問題を起こしているという実態が明らかになっています。
訪問販売によるトラブルが多い商品としては、ソーラーシステム、放送サービス、新聞が顕著であり、これらの訪問販売については特に注意が必要といえます。
※当事務所では、適正な訪問販売事業のための契約書雛形と特定商取引法に関する解説書を販売しております。訪問販売事業をされている事業者の方は下記リンク先のページもご参照下さい。