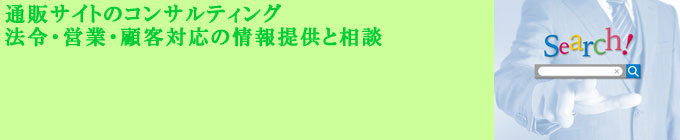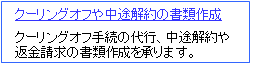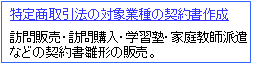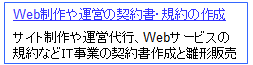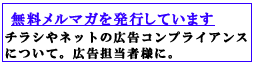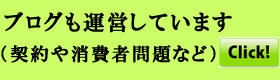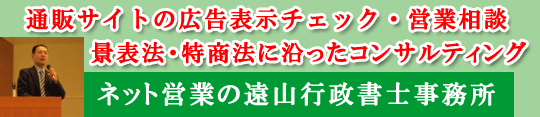
電話勧誘販売によるトラブルの相談件数は、国民生活センターの消費生活年報2009年度版によれば49,261件になっています。
これはピーク時の2003年度の108,751件と比較すると55%減少していますが、まだ多くの相談が各地の消費生活センターに寄せられています。
電話勧誘を行う事業者は、自社商品との関連性が強い属性の名簿を購入して、そのリストに基づいて営業電話をかけていることが推測されます。
そのため、複数の事業者が同時期に営業電話をかけるため、同じような商品の電話勧誘を受けることも多くなります。
何度も電話がかかってくるため、断り切れずに契約をしたり、過去に取引をした事業者と誤認をして新しい事業者と契約をするケースも多いようです。
電話勧誘は不意打ち性が高い営業方法であるため、規制や消費者保護の制度が必要になります。
特定商取引法では、電話勧誘については事業者の名称や勧誘の目的を明示する義務が定められ、8日間のクーリングオフ期間も設けられています。
こうした消費者保護の施策が奏功し電話勧誘の苦情相談は減少しています。
しかし、高齢者を狙った金融商品や各種権利の電話勧誘は依然として多く、被害にあった場合の損害は高額になる傾向があります。
※当事務所では、適正な電話勧誘販売事業のための契約書雛形と特定商取引法に関する解説書を販売しております。
電話勧誘販売事業をされている事業者の方は下記リンク先のページもご参照下さい。