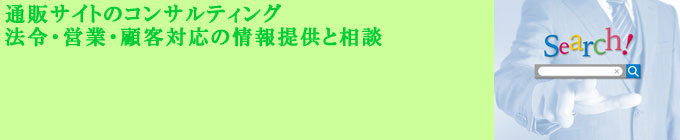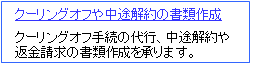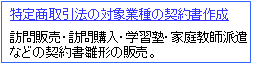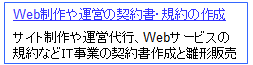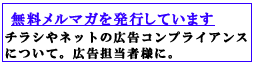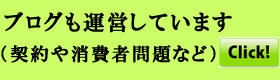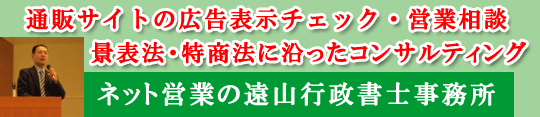
ホームページやチラシ等の広告は景品表示法等のルールに基づいて適正な表示をしなくてはなりません。
そうした広告の担当者は、強い営業的な訴求を追い求めるあまり不当表示を見逃してしまうと業務停止や課徴金などの処分を受けるリスクを抱えることになるため、広告表示のルールを学ぶ必要があります。
また、通販サイトやアフィリエイト、オークション、マッチングサイトなど、商用のホームページを運営するインターネットビジネスに関わる方は、WEB関連の技術動向やウェブマーケティング情報の他にもネット関連の法律に関する知識についても最新情報を把握する努力が必要です。
ウェブ制作者やウェブ担当者も情報セキュリティだけではなく、コンプライアンスや法律に関する知識を得てネット法令のリスク対策を実行しなくてはなりません。
インターネットビジネスの創生期では、WEB技術もIT関連法令も未整備であり“早くやったもの勝ち”という傾向がありました。
しかし、インターネットの普及から20年以上が経過し技術もマーケティングも法律も成熟期を迎えつつあります。
(それでも更なる情報技術の革新は続く見通しです)。
現在でネット創生期の頃の感覚で振る舞いをすると法律的にアウトになってしまうため、正しい知識を学習しておく必要があります。
そこでインターネットビジネスを運営していく上でチェックが必要な法令について挙げてみます。
(1)電子契約の成立要件を満たす(電子消費者契約法や電子商取引に関する準則)
(2)通信販売の法規制をクリアする(特定商取引法や消費者契約法)
(3)サイトの広告・表示の表現に留意する(景品表示法やその他の業法)
(4)サイトの著作権防御と他者の権利侵害を予防(著作権法)
(5)顧客情報管理や営業秘密の防御(個人情報保護法や不正競争防止法)
以上のチェックポイントについて運営サイトにルール違反があった場合には、それを放置すれば個別契約の取り消し(返金)や行政処分(営業停止など)を受けたり、ネットで悪評が拡散して事業の継続が危うくなるというリスクが高くなります。
そうしたリスクを知らずにビジネスを続けるのはとても怖いことです。
正しい法律とコンプライアンスの知識を学べば、そうした法律に関するリスクは予防できることですから、IT技術やマーケティングの知識だけではなくネット法令知識を身に着けたいところです。

ここに挙げた5つのチェックポイントを以下に解説します。
(1)電子契約の成立要件を満たす(電子消費者契約法や電子商取引に関する準則)
商用ホームページで売買契約を成立させるには、電子消費者契約法での電子契約成立ルールを把握して、サイト上の申込み画面の設計を行う必要があります。
これに違反した契約は無効とされ、商品の返品や返金に応じなければいけなくなります。
(2)通信販売の法規制をクリアする(特定商取引法や消費者契約法)
商用ホームページは、特定商取引法の通信販売の取引に類型され、重要事項の表示義務などの事業者規制とクーリングオフに類似した解約制度(法定返品権)などの民事ルールの適用を受けます。
これに違反した場合は、行政処分や契約取消などの不利益を被るリスクが高まります。
具体的にはサイトの申込フォームに同意した後には確認画面を設ける必要があります。
また、特定商取引法に基づく表示として以下の事項をサイトに掲示しなくてはなりません。
<インターネット通信販売サイトの表示義務事項>
1 販売価格(役務の対価)
2 送料
3 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭。その内容および金額
4 代金(対価)の支払い方法
5 代金(対価)の支払い時期 、商品の引渡時期
(権利の移転時期、役務の提供時期)
6 商品(指定権利)の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項
(返品の特約がある場合はその旨含む。)
7 商品に隠れた瑕疵(一見しただけではわからない不具合)がある場合
に、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容
8 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
9 事業者が法人であって、電子情報処理組織を使用する方法により広告
をする場合には、当該販売業者等の代表者または通信販売に関する業務
の責任者の氏名
10 いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェア
の動作環境
(3)サイトの広告・表示の表現に留意する(景品表示法やその他の業法)
商用サイトの売上向上を図るため、商品やサービスの広告は積極的に行うべきですが、その広告表現は何を書いても良いわけではなく、景品表示法の規制を受けます。
また、扱う商品・サービスによっては、その他の業法の規制を受けることもあります。
<景品表示法の不当表示の種類(禁止行為)>
(ア)優良誤認表示
製品の品質等の内容が実際よりも著しく優良であると表示すること。
(例)「過剰なダイエット効果の宣伝」「産地偽装の食品」など
(イ)有利誤認表示
製品の価格等の取引条件が実際よりも著しく有利に表示すること。
(例)「携帯電話がO円」「上げ底包装」「定価と売価の二重価格」など
(ウ)その他誤認の恐れのある表示(特定分野の表示)
・無果汁の清涼飲料水についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示
(4)サイトの著作権防御と他者の権利侵害を予防(著作権法)
ホームページを構成するテキスト・画像・動画などのコンテンツは著作物になります。
インターネット上にはそのようなコンテンツが無料で公開されていますが、その取扱いには注意が必要となります。
著作物の無断複製は違法行為となりますが、一定のルールを守って他人の資料を引用する場合は適法となります。
以下に著作物の引用のルールを例示します。(著作権法32条1項)
・既に公表されている著作物であること
・公正な慣行に合致すること
・報道・批評・研究などのための正当な範囲内であること
・引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確であること
・カギ括弧などにより引用部分が明確になっていること
・引用を行う必然性があること
このように自分で著作物を創作しようとしていることが、引用の大前提となります。引用が無ければ作者の主張の説明が不可能かどうかが、引用の適否の判断基準となります。
また、引用を行う場合には、その出典情報などの出所の表示義務もあります。(著作権法48条)
(5)顧客情報管理や営業秘密の防御(個人情報保護法や不正競争防止法)
現行の個人情報保護法は、「データを第三者提供する際には原則として本人の同意が必要」としているので、個人情報を取得する段階で利用目的を示して同意を得る手続をしておかなくてはなりません。
具体的には個人情報の送信フォームに「(個人情報は)当社の関連会社、関連サービスの事業に活用します」という趣旨を明示して、それに対して同意ボタンをクリックしてもらう等の措置が必要になります。
また、ビジネスの営業秘密を守るためには不正競争防止法の基準での情報管理が求められます。
不正競争防止法上の営業秘密の定義では、(a)秘密として管理されていること、(b)有用な情報であること、(c)公然と知られていないことの三要件を満たすものとされています。