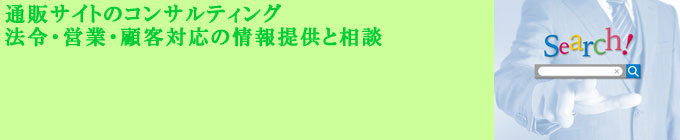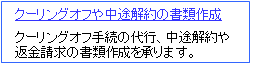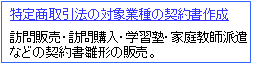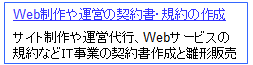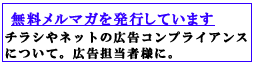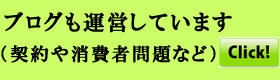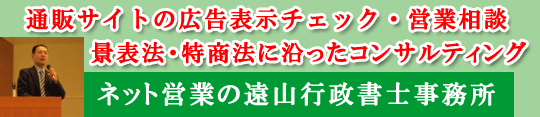
マルチ商法(連鎖販売取引)とは、一般消費者に商品(健康食品や化粧品など)を販売する権利(代理店、ディストリビューター)を認めて、販売組織への登録(商品の購入が前提条件となることが多い)を促し、その売上や新規登録会員の獲得数に応じて報酬(リベート、コミッション、ボーナス)を支払う仕組みのことをいいます。消費者が商品の販売組織に加入して、更に販売組織を拡大するために勧誘を続け、組織の下部人数を増やしていくピラミッド構造を基本形としています。
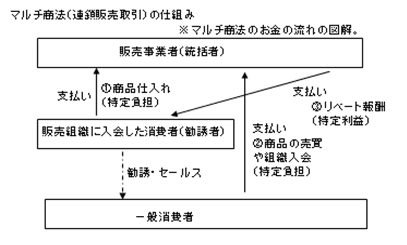
マルチ商法という名称の他にも、MLM(マルチ・レベル・マーケティング)やネットワーク・ビジネスと呼ぶこともありますが、内容は同じものです。
![]()
特定商取引法では、マルチ商法のことを「連鎖販売取引」という名称で呼び、20日間のクーリングオフ期間や中途解約のルール、勧誘時と契約時に交付する書面に取引の詳細を記載する義務などを定めています。
マルチ商法は法律でも認められた合法的な販売手法となりますが、特定商取引法で定められたルールを守らない販売事業者とのトラブルも多く報告されていて、注意が必要なビジネスということになります。
マルチ商法は、1930年代のアメリカで発祥しました。国土が広大なため、物流や店舗が整わない時期には訪問販売が盛んという背景もあったようです。マルチ商法は消費者の人間関係を利用した口コミで集客や販売をするため、販売事業者にとっては自社で訪問販売用の営業マンを雇ったり新聞広告に経費をかけるより、安価で効果的な営業方法ということで注目を浴びました。
取扱い商品が良質であり、消費者が納得をしてその商品の販売をするという初期の形態のうちは大きな問題にもなりませんでした。
しかし、その効率の良い販売方式が悪用され、粗悪な商品を売り込んで収益だけを目的としたり、無価値な商品を扱い実質的にねずみ講の隠れ蓑として活動をしたりする事件が相次ぎました。
日本国内では、1970年代にアメリカのホリディ・マジック社(化粧品)、APOジャパン(カー用品。後の円天会長)等がマルチ商法の販売形態を持ち込み、ピラミッド構造で会員を増やしましたが、最終的には多数の被害者を出して事業破綻しました。
それ以降、マルチ商法は悪徳商法と認識され、訪問販売法(現在の特定商取引法)によって厳しい規制がされるようになりました。
国民生活センターの消費生活年報2011年版によれば、近年のマルチ取引の苦情相談件数は2007年度には24,331件でしたが、2010年度には11,504件にまで減少しています。
しかし、大学生や新社会人の間で投資系商材のDVDのマルチ商法が流行したり、化粧品や健康食品などの分野では多くの会員を抱える販売組織が存在しており、その動向には注視が必要といえるでしょう。