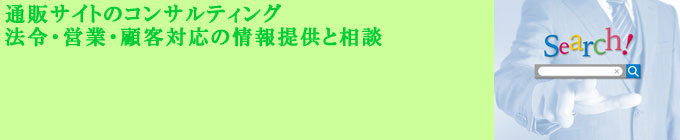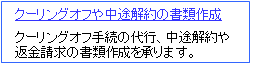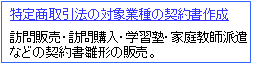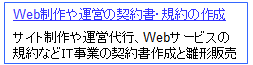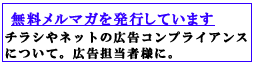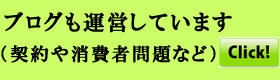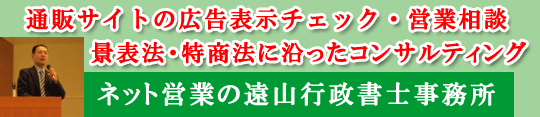
国民生活センターの消費生活年報2011年版によれば、貴金属の出張買取業者に関する苦情相談が2010年度(11月末までの集計分)は538件に上っています。前年度は137件なので、2010年に急増したトラブルといえます。
苦情相談の内容は、金やプラチナ製品などの買取をしてくれるというので消費者が貴金属を売ったところ、後で調べたら相場よりもかなり低額に評価されていることに気づき、返還請求したが応じてもらえないというケースが多いようです。
特に家庭へ訪問をしてくる出張買取業者は、強引に買取を勧めることも多いため、消費者が怖い思いをしたという事例も目立ちます。
従来からある“押し売り”ではなく、“押し買い”という新しいトラブルです。
業者が家庭に訪問をしてくる出張買取は、特定商取引法では規制の対象外になっていました。
そのため、クーリングオフのような契約を解除する制度がなく、解決が難しいトラブルだといえます。
あまりにも低すぎる金額で買取をさせられた場合は、錯誤や詐欺などを理由に契約無効を主張する余地はありますが、その事実証明は相当に困難なものになります。
(訪問買取は事業者と消費者間の取引であれば、消費者契約法の対象にはなります。同法の重要事項の不実告知や不利益事実の不告知による取消も検討は出来ますが、その事実証明は難しい面があります。)
こうした法の隙間を狙った取引形態を規制するため、特定商取引法の改正によって訪問買取を規制することになりました。
出張買取の業務を実施している事業者は、この訪問購入規制に沿った契約書面を準備する必要があります。
訪問購入の契約書(雛形)
消費者をだまし討ちにする悪質商法は、法規制をかいくぐり新しい手口が出現しています。
法改正で悪質商法を規制していくことも大事ですが、どうしても後追いになってしまいます。
被害拡大を防ぐためには、悪質商法の新しい手口を取り上げ、消費者への啓発を継続することが必要です。