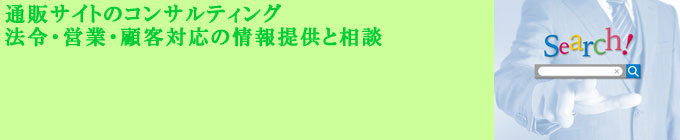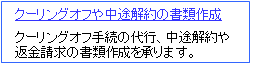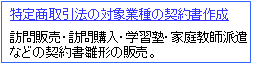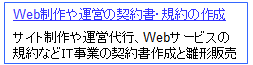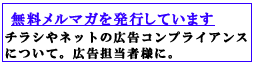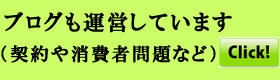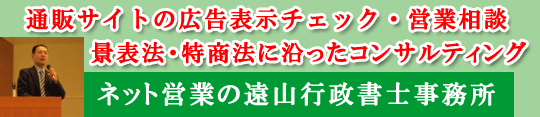
マイナンバーが通知され、会社では税務や労務の手続で従業員にマイナンバーを確認する作業が進む一方で、マイナンバー制度に便乗した詐欺行為への注意喚起もされています。
慣れない手続が始まることから、ネットではマイナンバーへの不信感の投稿も見受けられます。
マイナンバーがどのような目的で導入され、それが消費者にとってどのようなメリットがあり、注意をしなくてはならない事は何なのか、制度の正しい理解と冷静な対応をするための情報をまとめます。
マイナンバー制度とは
そもそもマイナンバー制度の目的については、政府広報では(1)行政の効率化、(2)国民の利便性の向上、(3)公平・公正な社会の実現だと告知しています。
例えば、様々な役所で国民一人一人に以下のような個別の番号が割り振られています。
住民票 :「住民登録番号」
年金 :「基礎年金番号」
健康保険:「保険者番号」
税金 :「整理番号」
これらをバラバラに運用していると様々な作業の重複やムダが生じ、それが行政コストの増大にもつながり、国民も手続が複雑で困ることが多くなります。
マイナンバー制度が導入されることにより、社会保障、税分野において統一の番号ができ、役所間の情報共有が容易になります。
そうなれば行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止することにつながり、行政サービスの公平性が高まります。
このようにマイナンバー制度の導入は行政サービスの質的向上を図る上で必要なものです。
勤務先からマイナンバーを尋ねられたら教えなくてはいけません
マイナンバーは役所の中だけで使用されるものではなく、国民一人一人に通知されます。
その通知されたナンバーを勤務先から調査されるようになります。
企業が従業員の税務書類等を作成する場合に、役所に提出する書類には従業員のマイナンバーを記載することが義務化されます。
しかし、マイナンバーは国民一人一人に直接通知されるため、企業はそれを把握できません。
そのため企業は従業員からマイナンバーを取得しなくてはならないのです。
「勤務先からマイナンバーを尋ねられたが教えなくてはいけないのか?」
「アルバイト先からマイナンバーを聞かれたが、それは問題ないか?」
このような問合せも多いのですが、企業にはマイナンバー取扱いが義務化されるため、従業員にマイナンバーの開示を求めるのは適法な業務であり、これには問題はありません。
(マイナンバー制度に対応して、就業規則に従業員のマイナンバー開示義務を設ける企業も増えており、開示を拒否すれば就業規則違反として罰則適用がされるケースもありえます。)
ただし、マイナンバーは重要な情報ですから、企業のマイナンバー担当者以外の人物には教えてはいけません。
もし、勤務先のマイナンバーの秘密管理が徹底されていないと感じたら、個人情報保護委員会の苦情あっせん窓口に相談することができます。
苦情相談あっせん窓口|個人情報保護委員会
マイナンバー制度に便乗した詐欺行為に注意
何か大きな事件や制度改革があると、それを口実とした詐欺行為が増える傾向があります。
マイナンバー制度も例外ではなく、これに便乗した詐欺が次々と現れています。
国民生活センターでは、マイナンバー制度に便乗して口座番号を聞き出そうとしたり、個人情報の削除を持ち掛けたりするなどの不審な電話に関するものの他、「あなたのマイナンバーが漏えいしている」などとして、別のサイトへのアクセスを誘導する不審なメールに関するものも寄せられていると警鐘を鳴らしています。
具体的には、以下のような事例が公表されています。
【事例1】「あなたのマイナンバーが漏えいしている」という不審なメールが届いた
【事例2】「サイト料金が未納になっている。放置するとマイナンバー制度により影響がある」という不審なメールが届いた
【事例3】「連絡しないとマイナンバーの交付ができない」という不審なメールが届いた
その他にも、ネットの通販サイトで注文したらマイナンバーを教えるように求められるなど、不正な方法でマイナンバーを収集しようとする悪質業者もいるかもしれません。
そのような手口にだまされないよう注意する必要があります。
徐々にマイナンバーを活用した取引が増えていく予定ですが、現時点では、勤務先と公的機関以外にはマイナンバーを教えてはいけないものとして対処するのがよいでしょう。
当事務所では、企業でマイナンバーを取扱う際のルール作りをサポートするため下記のリンク先で就業規則・個人情報取扱規程・秘密保持誓約書のひな形をセットにして販売しております。
マイナンバーと就業規則等のひな形セット
事業者としてマイナンバー取扱いをする立場の方は、上記リンク先ページもご参照下さい。