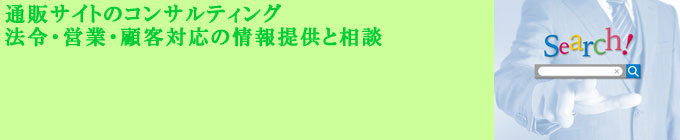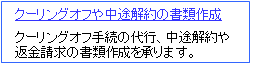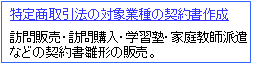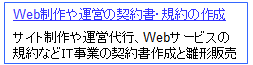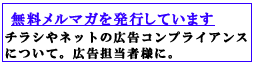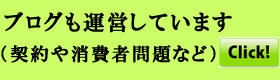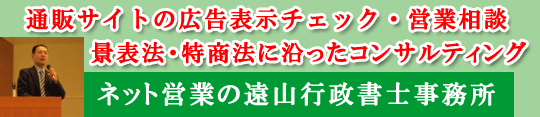
インターネットの普及によって、ネットやスマートフォンを利用する通信販売の市場は急速に拡大しました。
日本通信販売協会(JADMA)による2010年度のインターネット通販の売上高調査の統計値では、前年比8・4%増の4兆6,700億円となっています。
こうしたインターネット通販については、消費者が時間や場所の制約を受けずに買い物ができることからメリットが大きいものです。
また、インターネット上に通販サイトを立ち上げることは比較的容易にできるため、販売事業者の参入も増加し通販サイトの競争も激化しています。
そのような競争による通販サイトのサービス向上や価格低下は消費者の利益になるものですが、一方で営業経験の浅い事業者や悪質な事業者の参入によって契約トラブルも多発しています。
国民生活センターによる2010年度のインターネット通販に関する相談件数は、前年比18%増の155,885件にも上っています。
もともと通信販売は、商品を直接に手で触れて確かめることはできず、カタログ上の(サイトに表示された)情報を信用するしかないという特性があります。
そのため、実際に取り寄せたら、消費者が思い描いていた物とは違う誤認の問題は起きやすい取引形態といえます。
その上、事業者の競争も激しく、商品のセールスコピー(広告文)の内容も大げさな表現になることもあり、それが消費者の判断を誤らせることにもつながります。
それは、実際のものよりも著しく優良であると表示をする優良誤認や、実際のものよりも著しく有利であると表示をする有利誤認の問題を引き起こし、景品表示法等の表示規制に抵触することもあります。
インターネット通販では、サイト上に表示された情報だけが消費者の判断材料となるため、特にその表示については正確な表現が求められます。
しかし、現状は過大な広告表示も多く、監督官庁(消費者庁や都道府県)もいつも監視をしているわけではありません。
そのため、事業者のWEBサイトに過大な広告表示があったとしても見過ごされているのが実情といえるでしょう。
また、通信販売は消費者側から注文の意思表示をするため、日本においてはそこに不意打ち性はないとされています。
そうした前提があるため、特定商取引法の通信販売に関する規制でもクーリングオフ制度は認められていません。
但し、事業者がWEBサイトに適切な方法で返品に関する特約を表示していない場合は、消費者は契約解除ができるとされています。
この場合では、送料など返品に要する費用はクーリングオフとは異なり消費者が負担するものとなっています。
事業者がWEBサイトに返品の特約を適切に表示していた場合は、その表示内容が優先されます。
例えば、「商品納品後の返品は応じられません」との表示が適切な方法で行われていれば、その表示が優先され返品は不可能という扱いになります。
事業者側は表示を適切に行い、消費者側は表示内容をよく読んで納得してから注文をすることが必要です。