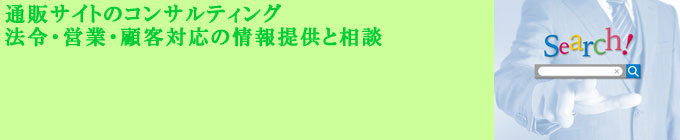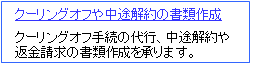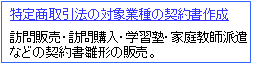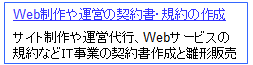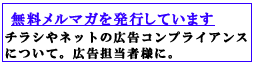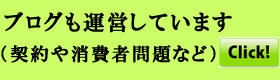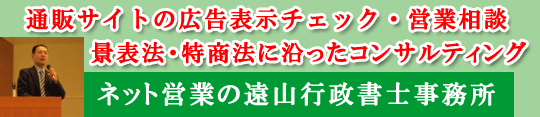
民法は1898年に施行された旧民法を基に1947年に改正民法が公布され、その後に口語化などの細かな修正はありつつも、契約の基本法として旧来の枠組みのまま今日に至っています。
2016年現在では、民法(債権法)改正の国会審議が進められていますが、現状では消費者と事業者の情報等の格差是正という視点が無く、消費者契約の問題については他の特別法の規定にはない隙間事案についてのみ民法を適用する形となっています。
契約法としての民法の基本原則
契約自由の原則と権利濫用の禁止
契約は当事者間の申込と承諾の一致があれば、その内容については原則として自由に定めることができるとされています。
この場面で契約当事者の力量の格差は考慮されていません。
ただし、公序良俗に反する契約内容は無効とされています。
また、当事者の一方が自己の権利を不当に拡大して解釈(濫用)することも禁止されています。
典型契約
民法に規定されている契約の種類は13種類です。
(売買・贈与・交換・賃貸借・使用貸借・消費貸借・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解)
この13種類の契約は典型契約と呼ばれています。
しかし、産業の高度化とともにリース契約などの民法の規定には無い新しい契約形態が次々と登場しており、民法の典型契約だけでは解釈できない事態が生じています。
そのような非典型契約については特別法で規定したり、業界の自主ルールで運営されたりしています。
瑕疵担保責任
商品やサービスの提供者は、その提供する商品について瑕疵(欠陥などの問題)があれば、それを修補する責任があります。
損害賠償責任
取引で相手方に損害を与えた場合は、被害者が被った損害について賠償をする責任が生じます。
ただし、その責任を追及するには、被害者側で加害者側に過失があったこと証明する必要があります。(過失責任主義)。
錯誤による無効
契約をする際の要素や動機に勘違い(錯誤)があった場合は、その契約を無効とすることができます。
ただし、錯誤の立証は容易ではありません。
詐欺・強迫による契約
詐欺や脅迫に基づいて行った契約は無効とすることができます。
ただし、詐欺や強迫を立証するのは容易ではありません。