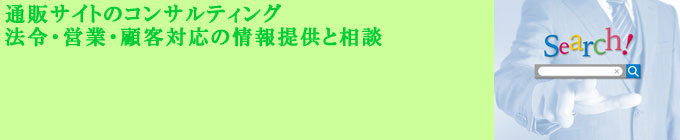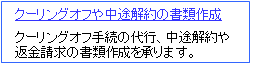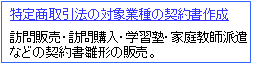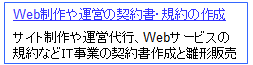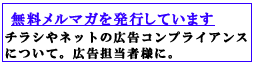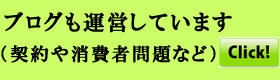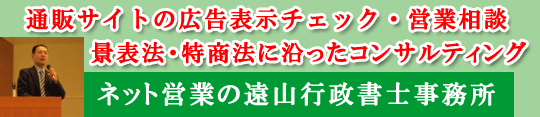
ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)とは、日記やメッセージ、ゲームなどを通じて友人や知人・共通の趣味を持つ人達との交流 を目的としたインターネット上のサービスの総称のことです。
ライン、スカイプ、フェイスブック、ツイッター、モバゲー、グリー、ミクシーなど、情報機器を持っている人なら複数のサービスを日常的に利用していることでしょう。
これらのサービスは、便利な道具であり正しく使う分には問題はありません。実際にラインやスカイプを友達同士の連絡手段やビジネスの情報共有のツールとして使ったり、災害時にツイッターやフェイスブックが大いに活躍したりという素晴らしい活用例は多くあります。
しかし、使い方を間違えると依存症になったり、様々なトラブルを引き起こす可能性があります。特に中学生・高校生や若い世代で高額課金や投稿内容の炎上騒動、恐喝、性犯罪などの問題が多発しています。
SNSは、スマートフォンとパソコンだけではなく、Wi-Fi(無線LAN)機能を通じてゲーム機、音楽プレーヤー、電子書籍リーダー、各種タブレットでも一部機能を利用することができます。これらの機器の全てを利用しないということは、現在の日本社会では事実上不可能といえる状況です。
つまり、パソコンとスマートフォンの使用を禁止したとしても、SNSに接する機会はあり、SNSを全く利用しないという状態を続けるのは難しいといえます。
それならばSNSを全面禁止するよりも、その危険性を事例から学び、節度のある適正な使い方を身に着けることの方が大切なはずです。
家庭や学校、職場において、SNSの利用法や制限について考える機会を設けるのがよいでしょう。
それでは、SNSトラブルとして代表的なものを挙げてみます。
・ソーシャルゲームの課金で短期間に数十万円を浪費した。
・SNSの依存症になり学校の成績や職場の能率が落ちた。
・SNSでの煽りや嫌がらせの発言に精神的ダメージを受けた。
・SNSで知り合った人に会って、性的暴行を受けた。
・別れた彼氏にわいせつな写真を拡散された。(リベンジポルノ)
・不適切な日記を書いたことが原因で恐喝を受けた。
・グループ内のイジメが陰湿になった。
・投稿内容が炎上して就職が取り消された。
・従業員が他者を誹謗中傷する投稿をして炎上し、会社に苦情が殺到した
・ストーカー(つきまとい)の被害にあった。
こうした問題は珍しいものではなく、広範に認められるほど事態が深刻になっています。
何の予備知識もなく無制限にSNSの利用を始めるのは危険性が高いと断言できます。
具体的な事例を知り、危険性を認識したうえで、適正な使い方を覚える必要があります。
インターネットの匿名性への誤解、コミュニケーションに必要な心遣い、トラブルに巻き込まれないための発言ルール、家庭・学校・職場での利用ルールなどをグループ単位で学ぶ機会を設けるとよいでしょう。
当サイト運営者の行政書士・遠山桂は、IT関連の契約書作成、ネット通販事業のコンサルティング、消費者教育の講演などで豊富な実績があります。
こうしたテーマでの講演・出前講座・研修・セミナーの講師を承ります。(全国対応します)
メールフォームよりお気軽にお問い合わせ下さい。
また、以下のようなSNS利用ガイドライン雛形、トラブル発生時の示談書の作成なども承っております。
SNSの適正利用に関する社内ガイドライン雛形(Web事業の契約書サイト)
社内のSNSトラブルを解決するための示談書(当職の運営サイト)