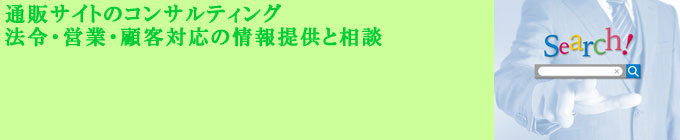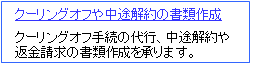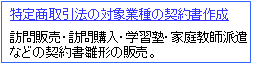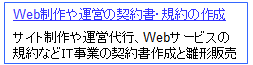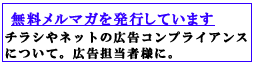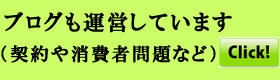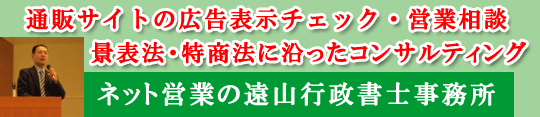
少子高齢化による国内市場規模の縮小などでビジネス環境全般としては厳しい状況が続きますが、インターネットビジネスの分野は好調です。
ホームページによるネット通販やアフィリエイト、個人輸出入、各種シェアリングなど小規模事業者が大きな売上を達成する事例を多く目にします。
経済産業省が公表した「平成27年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(電子商取引に関する市場調査)」によると、2015年度における日本国内の消費者向けEC(BtoC型)の市場規模は、前年比4.75%増の13兆7,746億円となっており、インターネット市場の拡大が続いていることが明らかになっています。
その一方で、インターネット通信販売を巡る消費者トラブルの増加も問題視されています。例えば、国民生活センターが公表するPIO-NETによせられたインターネット通販に関する苦情数は、2015年度では25万479件であり2011年度(17万8千件)との対比で40%も増加しています。
インターネット通信販売といえば、アマゾンや楽天のような大規模な事業者のサービスを思い浮かべますが、実際には小規模な事業者が多いことも特徴になっています。
経済産業省が公表した「消費者向け電子商取引実態調査」によれば、年間売上高1,000万円未満の事業者が全体の64%にあたる1万7,747で、3,000万円未満では80%に上ります。また、1事業者あたりの従事者数の平均は約3人となっています。つまり、日本国内の平均的なインターネット通販事業者像というのは、従業員数が3人程度で年商1,000万円未満という実態なのです。
そうした小規模事業やひとりビジネスで好調な売上を達成するケースも増えていますが、ホームページの運営や顧客対応などの業務の忙しさに追われて、表示した広告の内容に景品表示法などの法律に反する不当表示が行われていないかの自主チェックが不十分という実態もあるようです。
有利誤認や優良誤認の疑いのあるキャッチコピーや商品説明がサイトに表示されていると、行政による点検や消費者からの苦情申し出によって表面化し、景品表示法による行政指導や課徴金といった罰則が適用されるリスクがあります。
実際に東京都では生活文化局消費生活部取引指導課が2015年には366件(349事業者)もの行政指導を実施しています。
行政より不当表示のペナルティを受ければ、その悪評は瞬時にSNSで拡散され、その不名誉な事実が長くネットに残ってしまいます。
インターネットビジネスは顧客からの支持によって成り立つものですから、そのようなマイナス評価を背負うリスクは予防しておかねばなりません。
そうした不当表示リスクへの対策は売上好調の時に実施した方が効果的です。
なぜならビジネスに余裕があるときであれば、ホームページの広告表示の内容や顧客対応の点検をすることは無理なくできますが、売上が下降傾向のときには営業のテコ入れが優先されて広告表現も際どいものになってしまうことが多いからです。(そのために売上が下降傾向の時は不当表示リスクが高まって悪循環に陥ってしまう傾向があります)。