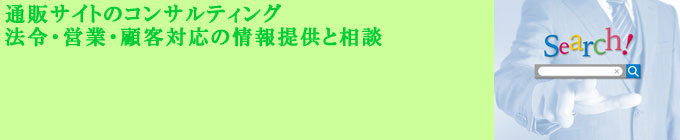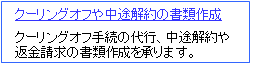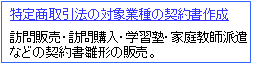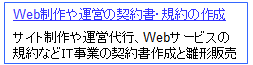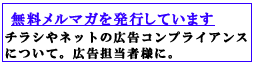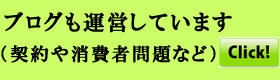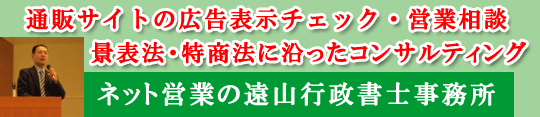
「値上がりが確実だから今買った方がいい」と語って、未公開株や社債などの儲け話をもちかけ、消費者に勧誘をする利殖商法(投資系の勧誘)の被害が甚大になっています。
国民生活センターの発表によれば、未公開株や社債については2001年から2010年までの累計被害額が860億円(2010年度だけでも283億円)に上っております。
警察庁の発表によれば、2010年度の振り込め詐欺の被害金額は82億円ですから、利殖商法による被害の方がより深刻になっています。
振り込め詐欺は、交通事故などの架空事件を理由に慰謝料などの名目で金銭を詐取することから、容易に詐欺と認定できるので、警察は振り込め詐欺に使われた銀行口座の凍結などを積極的に行っています。
そうした対策が奏功し、ピーク時よりも被害金額を半減できています。
しかし、利殖商法についてはペーパーカンパニーといえども証券が発行され、消費者も儲け話に応じたという面もあることから、刑事犯の詐欺と認定するまでのハードルが高く、救済が遅れているという実態があります。
民事の債務不履行や消費者契約法違反などは多数確認できても、2012年現在では即時に銀行口座を凍結するまでの法的根拠に乏しいということで、被害金の返還は困難になっています。
(悪質な販売事業者の財産を凍結し被害回復を図るために、消費者安全法などの法改正による対策の検討は進んでいます。)
また、こうした投資系の利殖商法で扱われる商材には、未公開株や社債の他にも、外国通貨や金の採掘権、温泉付き特養入居権や医療法人機関債などの実態の不透明な権利が用いられることが多くなっています。
このような新しい権利は次々と登場するため、販売される個別の商材の注意喚起をしただけでは追いつかないという問題もあります。
特定商取引法では、平成21年の法改正によりクーリングオフの指定商品制と指定役務制は撤廃され、訪問販売や電話勧誘販売による契約は原則として全ての商品とサービスについてクーリングオフが適用されるようになりました。
しかし、権利販売については従来の政令指定権利のみクーリングオフを認めているため、この指定権利のリストから外れる新しい権利を売り付ける悪質業者が増えているという事情もあります。
こうした法令のスキ間を狙う悪質商法が存在しているので、権利販売についても指定制を撤廃して、すべての権利販売についてもクーリングオフを認めるように法改正をする必要があるでしょう。
消費者被害救済のための法改正をはじめ、投資系の勧誘手口についての注意喚起と取締りの強化も求められます。